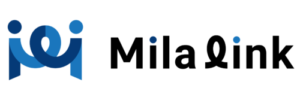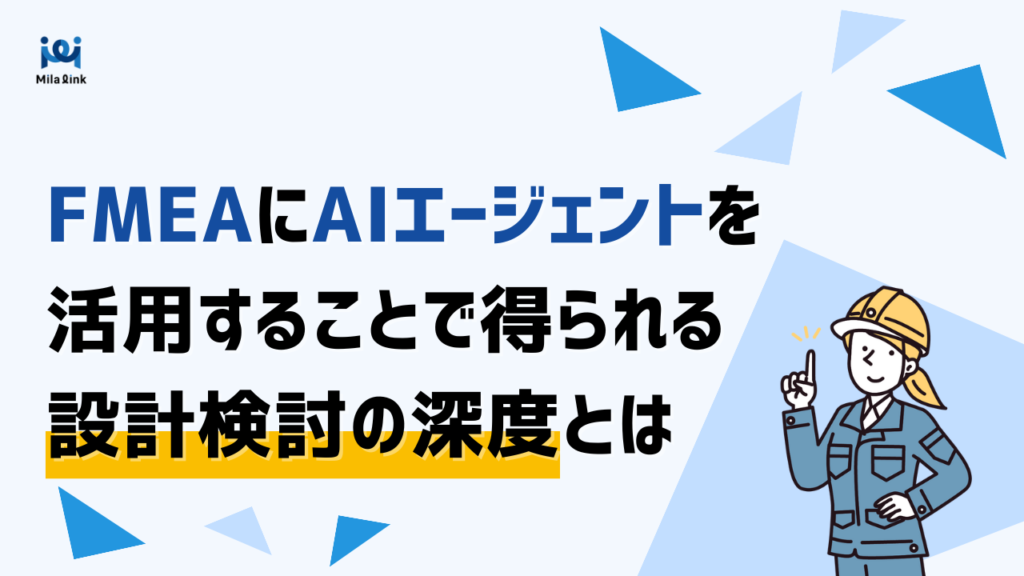
FMEA(故障モード影響解析)は、製造業の設計現場で広く使われている手法の一つです。
製品の潜在的な不具合を事前に洗い出し、対策を講じることで品質リスクを下げる目的があります。
しかし、現場レベルでは「FMEAが形骸化している」「毎回、同じような内容を繰り返しているだけ」といった課題に直面している企業も多いのではないでしょうか。
特に多いのが、FMEAの中身が担当者の記憶や経験に強く依存しているケースです。
ベテラン社員の頭の中には数多くの過去事例やトラブル事例が蓄積されていますが、それがうまく共有されず、若手や別部署の設計者には見えない“暗黙知”として埋もれてしまっています。
この状態では、FMEAが本来持つリスク低減の効果を最大限に引き出すことはできません。

佐取 直拓
ミラリンクでは、設計に関するお悩みについて
無料の相談会を実施しております。
設計AIエージェント「タグっと」について知りたい方はもちろん、設計ノウハウ活用やデータ整理の方法についてなど、設計に関するどんなお悩みでもご相談可能です!
以下のリンクよりお申し込みください。
無料相談会を予約する!
担当者の「経験」頼みでは限界があるFMEA運用

FMEAを実施する際、多くの現場では過去のテンプレートや前回品の内容をベースに作成を始めることが一般的です。
そして「前回はこのリスクを洗い出したから、今回も入れておこう」「確か以前こんな問題があった気がする」という記憶をたどって内容を追加していきます。
ところが、このやり方には以下のような限界があります。
- ベテランの経験がないと十分な網羅性を確保できない
- 部品の仕様が微妙に違っても、リスクの洗い出しが流用に偏る
- 記録として残っている資料が分散しており、検索に時間がかかる
- 担当者によって記述の深さや視点にばらつきが出る
こうした状態では、せっかくFMEAを実施しても、想定されるリスクが見逃されてしまったり、再発防止策として機能しないことも起こり得ます。
AIエージェントで過去知見を「検索可能」にする
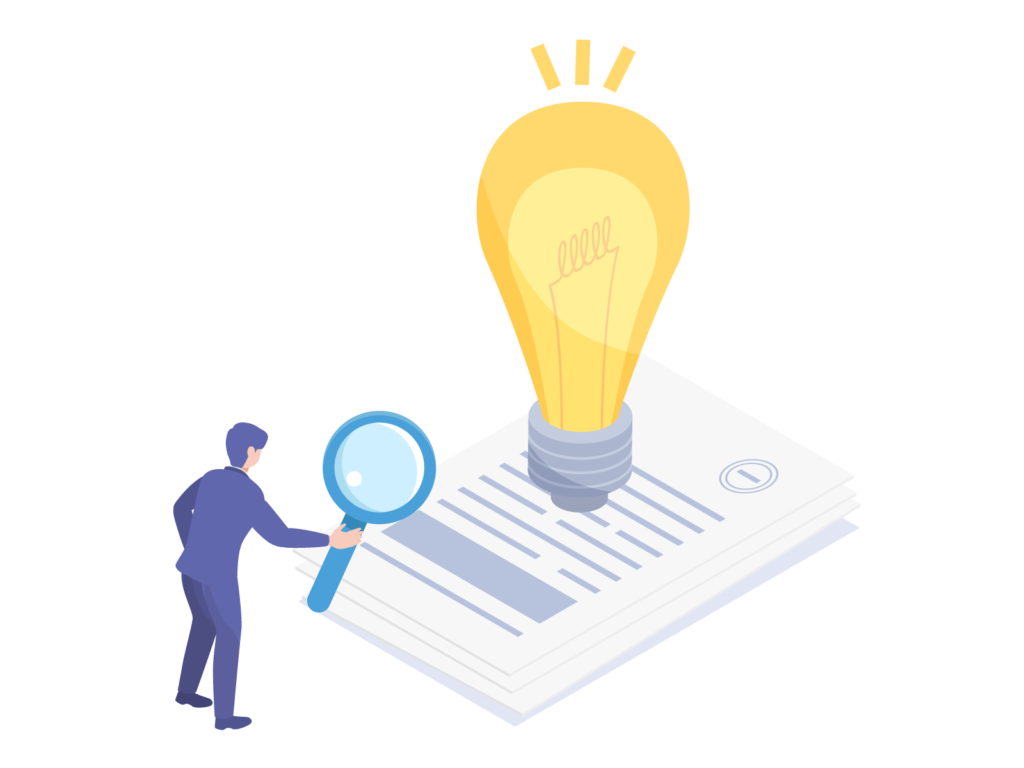
ここで効果を発揮するのがAIエージェントの導入です。
AIエージェントは、社内に蓄積されたFMEA資料、不具合報告、技術報告書、設計レビュー記録などのデータを横断的に学習・検索できる仕組みを持っています。
たとえば、ある部品に対するFMEAを作成する際に、AIエージェントに「このタイプの樹脂ギアで過去にどんな故障が起きているか」と質問すると、類似形状・類似用途の過去事例から故障モードのリストや、それに対応する原因、影響、検出方法まで引き出してくれます。
人間の記憶では思い出せないような古い案件でも、AIは漏れなく探し出します。
しかも、単なるキーワード検索ではなく、「構造が似ている」「環境条件が近い」といった文脈的な類似性も加味して提案されるため、従来よりも精度の高いFMEA作成が可能になります。
履歴の可視化と若手の立ち上がり支援にも効果
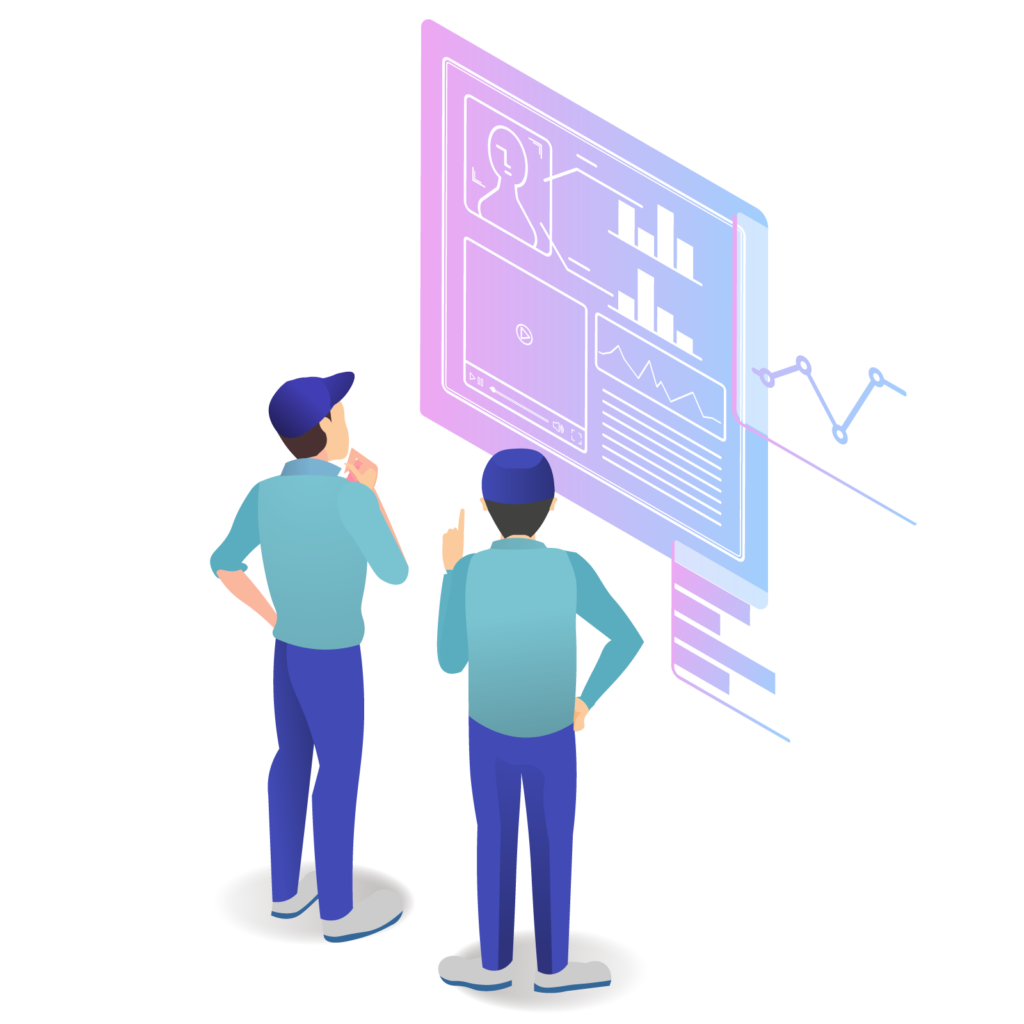
AIエージェントの活用は、属人化を防ぐだけでなく、若手設計者や異動者の業務理解を加速するという副次的な効果もあります。
FMEAの過去事例を自然言語で照会できるようになることで、経験が浅くても「なぜこの故障モードを考慮したのか」「どんな対策が過去に効果的だったのか」といった“判断の背景”まで追えるようになります。
これは、ベテランのノウハウを形式知化し、チーム全体の設計品質を底上げすることにつながります。
また、過去事例を手軽に引き出せる環境が整えば、FMEAのレビューや再発防止活動にも活用しやすくなり、品質保証との連携もスムーズになります。
実践ステップ:まずは対象を絞って導入
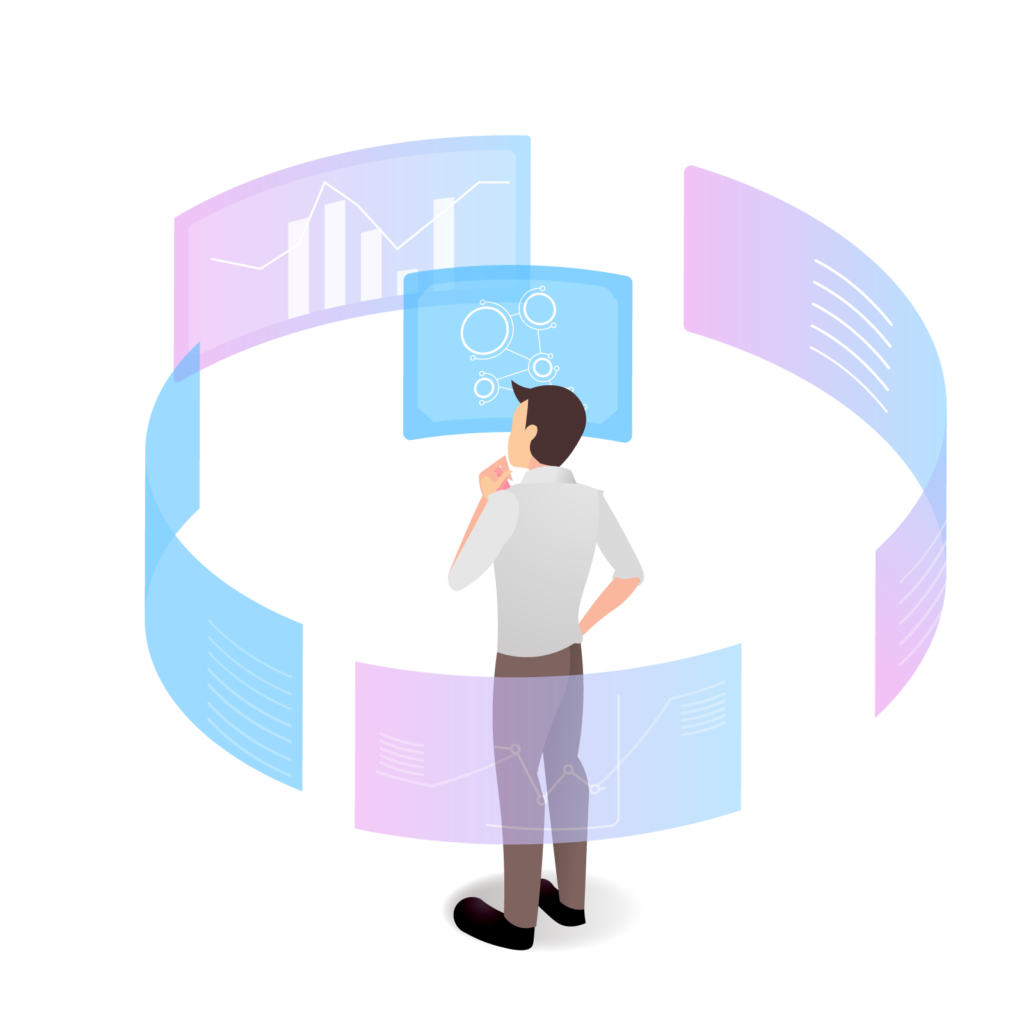
AIエージェントによるFMEA支援は、一気に全製品・全データに適用する必要はありません。まずはよく使われる設計要素や、トラブルが起きやすい部品カテゴリに絞って、過去事例を収集・整理し、AIに学習させるところからスタートするのが現実的です。
- 社内にあるFMEA資料や不具合報告書を収集・分類する
- 対象部品やプロセスごとにAIに学習させる範囲を設定する
- 設計担当者が日常的に使う検索インターフェースを用意する
- 試験的な運用を通じて、使いやすさと精度を検証する
このプロセスを繰り返すことで、社内全体にFMEA支援AIの活用が広がり、属人性の排除と効率的なナレッジ活用が定着していきます。
“設計特化” 検索AIエージェント「タグっと」
計AIエージェント「タグっと」は、設計にまつわる「ノウハウの検索」や「図面の検索」「資料の半自動生成」など、日々の業務を効率化するツールです。

タグっとを導入することで
・属人化していた設計ノウハウの可視化・再活用
・過去図面・資料のスムーズな検索と流用
・作業時間の削減と品質の安定化
など、現場の課題解決が期待できます。
また、今後は過去のトラブル事例や設計データをもとに、FMEAを半自動生成する機能の追加を予定しております。
タグっとについてご興味がある方は
以下より資料をご覧いただけます。
タグっとの資料をダウンロードする
まとめ
FMEAを「実効性のある設計ツール」に変えるためには、個人の記憶に頼らない仕組みが必要です。AIエージェントの導入によって、過去の失敗や成功の履歴を確実に再利用できる環境を整えることで、設計検討の深度が格段に向上します。
設計担当者が「何を考慮すべきか」に集中できるFMEA体制を整えることは、品質の向上と業務の効率化を同時に実現するための一歩です。まずは小さな範囲から、記憶に頼らないFMEAづくりを始めてみませんか?その積み重ねが、設計部門全体の底力につながっていきます。