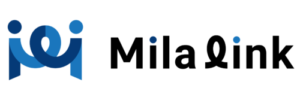3D CADによるモデリングは、製造業の設計現場において今や欠かせないツールです。
しかし、設計の自由度が高まる一方で、「モデル内の干渉が見落とされていた」「ねじや穴の位置が微妙にずれていた」「構成部品の厚みや強度に不整合がある」といった設計ミスが発見されるケースも少なくありません。
こうした初期段階のミスは、後工程での手戻りや不具合につながるリスクをはらんでいます。
そこで注目されているのが、AIエージェントを活用して3D CADモデルの中に潜む設計ミスを自動で検出する最新手法です。
設計者自身では気付きにくい小さな不整合を、AIが事前に指摘してくれることで、設計品質の向上と手戻り防止につながる仕組みとして導入が進みつつあります。

佐取 直拓
ミラリンクでは、設計に関するお悩みについて
無料の相談会を実施しております。
設計AIエージェント「タグっと」について知りたい方はもちろん、設計ノウハウ活用やデータ整理の方法についてなど、設計に関するどんなお悩みでもご相談可能です!
以下のリンクよりお申し込みください。
無料相談会を予約する!
設計ミスの典型例はなぜ起きるのか?
設計ミスの多くは、決して技術的な理解不足から生じるものではありません。むしろ、「確認する時間が足りなかった」「別パーツとの整合性を見落とした」「規格の反映漏れがあった」といった、業務の煩雑さや多忙さによる“うっかりミス”が原因であることが多いのです。
たとえば、以下のような事例は現場でもよく見られます。
- ボルト穴とボルトがわずかにズレていて組立時に干渉
- 隣接部品とのクリアランス不足で動作不良が発生
- 強度要件を満たしていない肉厚設計
- 公差設定が一部の面で抜けている
- 部品番号の命名ミスによるBOMの不整合
こうした細かな見落としは、設計段階では気づきにくく、図面化や試作段階になって初めて発覚することが多いため、対応が遅れると開発スケジュールに影響を及ぼしかねません。
AIエージェントの仕組みと導入例
AIエージェントによる設計ミスの検出は、以下のような仕組みで行われます。
- CADデータ(3Dモデルやアセンブリデータ)をAIに読み込ませる
- 形状や寸法、公差、材料情報などの構造データを解析
- 過去の設計事例や不具合データと照合し、類似するミスを検出
- 問題の可能性がある箇所を可視化し、設計者に提案
このプロセスを通じて、従来はレビューや手作業のチェックに頼っていた部分を、AIが支援してくれるようになります。特に、同じような形状が繰り返し使われる筐体設計や治具設計では、パターン認識の能力が高いAIが真価を発揮します。
活用シーンと設計者の負担軽減効果
AIエージェントの活用は、以下のようなシーンで実用的です。
- 設計レビュー前の自主チェックとして
- 試作前の構造一貫性確認に
- 他部品とのクリアランス自動検証
- 図面への落とし込み時の公差チェック支援
- 標準化されていない命名・属性ルールの確認
これにより、設計者は1件ずつの項目を目視でチェックする負担から解放され、より上流の仕様検討や機能設計に集中できるようになります。また、若手設計者にとっても「どこを見ればよいか分からない」という不安を解消する補助ツールとなり、教育や品質確保の面でも有効です。
今後の可能性と注意点
今後は、AIエージェントが学習するデータの質と量がさらに高まることで、より高度なミスの予測や、「設計意図との乖離」の指摘といった発展も期待されています。一方で、すべてをAIに任せるのではなく、「最終判断は人が行う」という前提で活用することが重要です。
AIはあくまで“補助”の役割であり、設計者の意思決定を支えるパートナーとして位置づけることが、活用の鍵になります。
“設計特化” 検索AIエージェント「タグっと」
計AIエージェント「タグっと」は、設計にまつわる「ノウハウの検索」や「図面の検索」「資料の半自動生成」など、日々の業務を効率化するツールです。

タグっとを導入することで
・属人化していた設計ノウハウの可視化・再活用
・過去図面・資料のスムーズな検索と流用
・作業時間の削減と品質の安定化
など、現場の課題解決が期待できます。
また、今後は過去のトラブル事例や設計データをもとに、FMEAを半自動生成する機能の追加を予定しております。
タグっとについてご興味がある方は
以下より資料をご覧いただけます。
タグっとの資料をダウンロードする
まとめ
3D CADの設計作業は高度化・複雑化する一方で、見落としやすい細かなミスが開発全体に与える影響は決して小さくありません。AIエージェントを活用すれば、過去のミスに学びながら設計モデルを自動的にチェックし、設計者にとっての「第2の目」として機能します。
設計精度を上げたい、手戻りを減らしたい、若手の設計支援を強化したい――そんな現場課題に対し、AIの力を借りてみてはいかがでしょうか。まずは自社のCAD運用の中で、AIが補える領域を見つけるところからスタートしてみると良いでしょう。設計の質とスピードを両立させる、新たな一歩になるかもしれません。