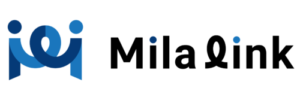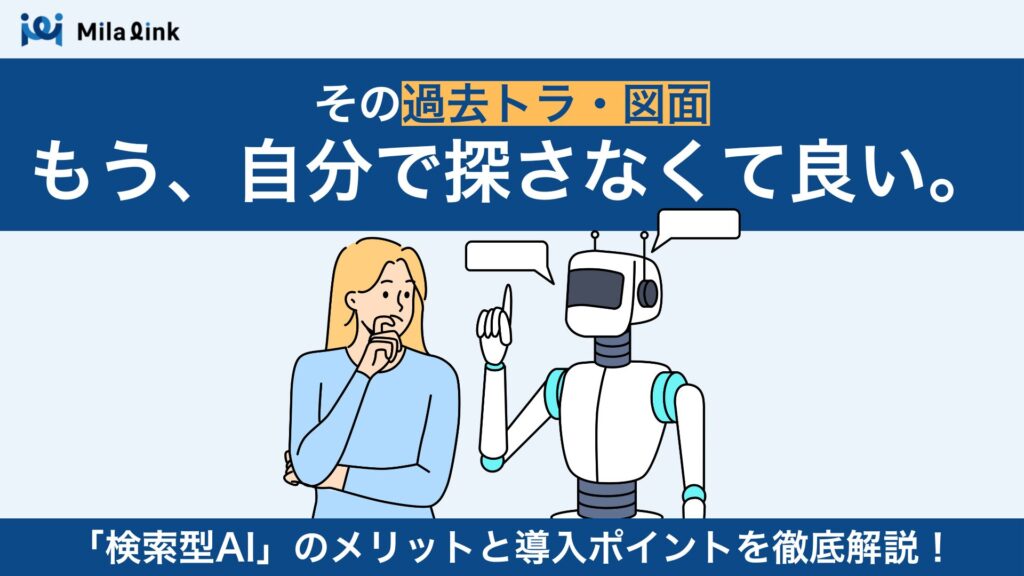
図面を探すのに30分、過去の不具合事例を見つけるのに1時間……。
設計担当者なら誰しもが経験する、そんな“探す作業”に追われる日々。設計の本質は「考えること」にあるはずなのに、情報を見つけるだけで膨大な時間と労力を使ってしまっていませんか?
そんな現場の悩みに対して、今、静かに革命を起こしつつあるのが「検索型AI」の活用です。最近では、PLMや設計ツールと連携し、自然言語で「聞けば出てくる」AIチャットが登場。検索にかかる時間や手間を大幅に減らし、設計者が本来の業務に集中できる環境づくりが注目を集めています。
この記事では、検索型AIがどのように設計業務の常識を変えつつあるのか、その仕組みや活用のメリット、導入時に押さえておきたいポイントなどを詳しく解説します。
AIが資料探索をどう効率化し、設計業務にどんなインパクトを与えるのか、ぜひ確認してみてください。

佐取 直拓
ミラリンクでは、設計に関するお悩みについて
無料の相談会を実施しております。
設計AIエージェント「タグっと」について知りたい方はもちろん、設計ノウハウ活用やデータ整理の方法についてなど、設計に関するどんなお悩みでもご相談可能です!
以下のリンクよりお申し込みください。
無料相談会を予約する!
設計者の時間を奪う「情報検索」の課題とは

設計業務には多くの創造的な作業が含まれますが、実際の業務時間のかなりの割合が「情報を探すこと」に費やされているのが実情です。
たとえば、新たな製品仕様を設計する前に、過去の類似設計や不具合履歴、社内標準、設計変更記録などを確認する必要があります。
しかし、それらの情報はPLM、ファイルサーバー、共有ドライブ、メール、紙の資料など、さまざまな場所に点在しており、検索に時間がかかるのが現場の共通課題です。
さらに問題なのは、資料の在りかが属人的になっている点です。特定の設計者しか知らない資料名や保存場所、あるいは略称やバージョン違いなど、検索には経験と勘が求められます。
若手エンジニアや異動直後のメンバーにとっては、この検索作業だけでも大きなハードルとなり、業務の立ち上がりが遅れる原因にもなっています。
一方で、設計ミスや手戻りのリスクを避けるためには、過去の事例や標準への準拠は欠かせません。
情報が見つからないからといって“勘”や“前例主義”で設計を進めてしまえば、後工程での不具合や手戻りにつながる可能性が高まります。
このように、「必要な情報にたどり着けない」ことは、時間的なロスだけでなく、設計の品質や再現性にも直結する重大な課題なのです。設計担当者が本来の業務に集中するためには、まずこの情報検索の負担を軽減する仕組みが必要不可欠です。
検索型AIが変える設計業務の常識

こうした情報検索の課題に対して、今、設計部門で注目されているのが「検索型AI」の導入です。
従来のキーワード検索やファイル階層による探索ではなく、自然言語で「〇〇の図面が見たい」「この部品の過去トラブルを教えて」などと“聞く”だけで、AIが社内のPLMやファイルサーバー、設計マニュアルから該当情報を探し出してくれます。
この仕組みは、RAG(Retrieval-Augmented Generation)と呼ばれる技術をベースにしています。
AIが外部のLLM(大規模言語モデル)と社内のドキュメント検索エンジンを組み合わせ、質問に対して根拠付きで回答を生成するため、単なるFAQとは異なり、複雑な質問や曖昧な言い回しにも対応可能です。
回答には常にファイル名やドキュメントIDなどの引用元が添付されるため、設計判断の裏付けとしても使える点が現場から高く評価されています。これにより、「なんとなくこうだった気がする」といった曖昧な知識ではなく、明確な根拠に基づいた判断が可能となり、品質とトレーサビリティの向上にもつながっています。
つまり、検索型AIは単なる業務効率化ツールではなく、「設計の判断基準を可視化し、再利用可能な知見として社内に蓄積する」ためのインフラとなりつつあるのです。
なぜ今、検索型AIの導入が進んでいるのか

検索型AIが設計現場に急速に広まりつつある背景には、単なる技術の進化だけではない、現場のリアルな課題と変化があります。特にここ数年で、導入のハードルが大きく下がり、実用レベルに達したことが大きな理由です。
まず一つ目のポイントは、情報の探し方そのものが変わってきたことです。若手の設計者は、複雑なフォルダ構造を掘って資料を探すよりも、「とりあえずチャットで聞く」ことに慣れています。SlackやTeamsなどの業務ツールが浸透する中で、検索に時間をかけず、すぐに答えが返ってくるスタイルが求められるようになったのです。
また、熟練者の持つノウハウの継承が難しくなってきているという現実もあります。ベテラン設計者が知っている「昔の不具合」や「社内ルールの背景」などは、文書化されていないことも多く、いざという時に後輩が調べようとしてもたどり着けない。そうした“属人的な知識”を、AIが資料の中から探して提示してくれることに、大きな価値が生まれています。
さらに、導入してすぐに効果が実感できるという点も、検索型AIが選ばれる理由の一つです。複雑な設定や学習をせずとも、すでにある図面や仕様書を対象に、AIが自然言語で検索できるようになることで、「いちいち探さなくていい」という体験を、現場の誰もがすぐに味わえるのです。
こうした背景から、検索型AIは単なる流行ではなく、「設計者が本来の仕事に集中するためのツール」として受け入れられ始めています。実際に導入している企業の多くが、数ヶ月以内に効果を実感し、現場定着を進めているという声も少なくありません。導入の決め手は、「使ってみたら、もう戻れない」というシンプルな体験にあります。
現場で成功するための導入チェックポイント

検索型AIは導入しただけで効果が出るものではありません。設計業務の中で自然に使われるためには、事前の準備と現場に合った運用設計が欠かせません。ここでは、導入を検討する際に特に重要となるポイントを4つにまとめてみました。
① どのデータをAIに見せるかを明確にする
まず最初に必要なのは、「AIに何を探させるのか」をはっきりさせることです。PLM上の図面、設計標準、変更記録、古いPDFマニュアルなど、社内には様々な情報がありますが、すべてを対象にするとノイズが増えてしまいます。
実際に成功している企業では、「この分類の資料だけはAIに聞ける」というルールを決めたうえで、アクセス権や機密情報の取り扱いも含めて制御しています。
PLMや社内共有フォルダと連動して、“見せてはいけない情報”を自動でマスクする仕組みを組み合わせているケースも多く見られます。
② 日常の流れに組み込まれたUIで使いやすさを確保
検索型AIは「使われてナンボ」です。TeamsやCAD、PLMの画面からそのまま質問できたり、「Alt+Space」で起動できるショートカットなど、現場の作業を止めずに使える導線があると、定着率がぐっと高まります。
とくに若手や新任者ほど、従来のフォルダ検索に不慣れな場合もあり、「とりあえずAIに聞く」が自然な選択肢になるようなUIの工夫が鍵になります。
③ 対象の業務を絞り、最初は“小さく始める”
いきなり全社展開するのではなく、設計標準の検索、過去不具合の参照、社内用語の説明など、「AIに聞くと便利そうなシーン」から試すのがおすすめです。
範囲を絞ることで現場の反応も得やすく、改善もしやすくなります。
いくつかの業務に定着してから、段階的に対象範囲を広げることで、スムーズに運用が広がっていきます。
④ 効果を“見える化”して、チームに浸透させる
便利さを実感していても、「本当に効果が出ているのか?」と聞かれたときに答えられないと、継続投資は難しくなります。
初回の回答率や平均検索時間の短縮、回答に引用元が添付されている割合など、数値で効果を見せられる仕組みがあると、現場にも納得感が生まれます。
“設計特化” 検索AIエージェント「タグっと」
計AIエージェント「タグっと」は、設計にまつわる「ノウハウの検索」や「図面の検索」「資料の半自動生成」など、日々の業務を効率化するツールです。

タグっとを導入することで
・属人化していた設計ノウハウの可視化・再活用
・過去図面・資料のスムーズな検索と流用
・作業時間の削減と品質の安定化
など、現場の課題解決が期待できます。
また、今後は過去のトラブル事例や設計データをもとに、FMEAを半自動生成する機能の追加を予定しております。
タグっとについてご興味がある方は
以下より資料をご覧いただけます。
タグっとの資料をダウンロードする
まとめ
検索型AIの導入によって、設計現場では「情報を探す時間」が確実に短縮されつつあります。
図面やマニュアルをいちいち掘り起こすことなく、自然な言葉で質問すればすぐに必要な情報にたどり着ける──そんな新しい情報活用のスタイルが、すでに多くの現場で注目されています。
設計ミスの予防や若手のスキルキャッチアップ、属人化の解消といった副次的なメリットも期待されており、「とにかく探すのが面倒だった」という日常の小さなストレスが解消されることで、設計者が本来の仕事に集中できる時間が増える可能性があります。
ポイントは、“誰でも・すぐに・自然に”使える設計にすること。AIはあくまで支援ツールであり、それをどう現場に馴染ませるかが導入成功のカギになります。
社内の情報を「探す」から「活かす」へのシフトを始めることで、設計の現場にもっと余裕と確実さを取り戻せるはずです。
あなたの職場では、情報を探す時間にどれくらい取られているでしょうか?
ぜひ、一度社内の情報活用の状況や情報収集にかける時間を見直してみてください。